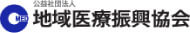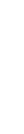呼吸器外科診療のご案内
当科の特長
2024年04月より呼吸器外科専門外来を常勤医である堀尾が担当することとなりました。私はそれまで都立駒込病院呼吸器外科に20余年勤務し、5,400件(うち肺がん症例約3,000件)あまりの手術症例を経験させていただきました。資格として呼吸器外科専門医、呼吸器専門医・指導医、気管支鏡専門医・指導医、日本外科学会専門医・指導医、日本内視鏡外科学会評議員、日本呼吸器外科学会特別会員、日本肺癌学会特別会員を有しています。当科では肺がんのみならず、転移性肺腫瘍、気胸、縦隔腫瘍、炎症性肺疾患などの胸部疾患に対する外科治療を行っています。
呼吸器外科外来は毎週水曜日の午前・午後となっております。
◇肺がんについて
肺がんは本邦において年間約12万人が罹患し、7万人が死亡する、がんの中で最も死亡数が多い病気です。肺がんになる人は40代後半から徐々に増加し、50歳以降になると急激に多くなります。日本人が生涯のうちに肺がんになる割合は男性で7.4%、女性で3.1%といわれています。肺がんの全臨床病期の5年生存率を見ると、相対生存率(がん以外の死因による死亡を除いたもの)は43.6%と算出されており、乳がん(93.9%)、大腸がん(76.6%)、胃がん(74.6%)と比べて治りにくいがんであることは否めません。しかし、早期の肺がん(Ⅰ期:腫瘍の大きさが4㎝以下で、リンパ節転移や遠隔転移のないもの)であればその相対生存率は82.0%に上昇し、早期発見・早期治療が生存率向上に重要であることがお分かりいただけると思います。職場や自治体の実施するがん検診で胸部異常影や喀痰細胞診陽性を指摘され、要精査となった場合は呼吸器内科・外科を問わず、すぐに受診されることをお勧めします。
当院で実施可能な検査は胸部CT、脳MRI、骨シンチグラフィ、気管支鏡検査、CTガイド下経皮生検です。なお、PET検査は近隣の実施可能な施設にお願いしています。
治療方針は呼吸器内科、呼吸器外科、放射線科、病理科などが協議して最適な方法を選択しています。
また、他施設へのセカンドオピニオンも随時行っております。
手術は6cm前後の小さな傷に胸腔鏡を併用した胸腔鏡補助下手術を行っています。これは「安全性」、「根治性」、「体への負担」の3者のバランスがとれた優れた方法であり、手術時間は標準的な肺葉切除・区域切除+リンパ節郭清では3時間前後、部分切除では約1時間、退院は肺葉切除・区域切除では術後5-6日、部分切除では術後3-5日で可能となっています。なお、肺がんの手術についてはクリニカルパスを導入し、患者さんに入院から手術そして退院までの治療計画を分かりやすく説明しています。また、他のがんと同様に、術後最低5年間は厳重に経過観察を行っています。
◇転移性肺腫瘍について
肺は他部位にできたがんが転移しやすい臓器です。過去にがんの治療歴があり、新たに肺に病変を認めた場合には転移の可能性があります。また、原発性肺がんや炎症性のしこり(何らかの感染によることが多い)の場合もあり、確定診断のために生検や切除を行う必要が生じることがあります。仮に転移であっても、肺の病変が切除可能な部位・個数であれば切除により治癒が望めます。手術の対象となりやすい転移性肺腫瘍は、大腸がん、腎臓がん、子宮がん、乳がん、骨軟部悪性腫瘍(骨肉腫など)です。
手術の大半は2㎝程度の傷が2-3か所の完全胸腔鏡での切除を行っており、手術時間は1時間程度、術後3-4日での退院が可能となっています。
◇気胸について
気胸はやせ型高身長の若い男性に多く見られる疾患ですが、高齢化社会とともに高齢者の気胸も確実に増加しています。高齢者の気胸は喫煙に関連する肺気腫・間質性肺炎などの基礎疾患による難治性のものが多いのが特徴です。一方、女性の気胸も増加しています。女性の場合、いわゆる月経随伴性気胸と呼ばれる生理と同期して気胸が起こる珍しい病態やLAM(リンパ脈管筋腫症)と呼ばれる稀少肺疾患が隠れていることがあり、女性気胸は注意が必要です。
手術は再発例、両側同時例、出血を伴う例、空気漏れが持続する例が適応となり、2㎝程度の傷が2か所の完全胸腔鏡下で、空気漏れの原因となっている肺嚢胞(ブラ)切除を行っています。また、初回気胸は手術の絶対適応ではありませんが、受験や海外出張を控えているなどの社会的な適応があれば手術を行います。手術時間は1時間程度、術後2-3日での退院が可能となっています。なお、手術を行っても100%再発が防止できるわけではなく、体質的に“空気漏れしやすい肺”であるため、5-10%に術後再発が認められるという報告があります。
◇縦隔腫瘍について
『縦隔』は左右の肺の間の領域を指す場所の名前で、臓器の名前ではありません。縦隔には首から胸、腹を繋ぐ臓器の通り道で、心臓をはじめ多くの重要臓器が存在します(食道もこの領域に存在しますが、食道にできる腫瘍は縦隔腫瘍に含めないのが通例です)。外界とのつながりがなく、いくつかの骨に囲まれて、病巣があっても容易に到達できない場所であるため、質的診断が困難な場合が多い領域です。代表的な疾患としては胸腺関連腫瘍(胸腺腫、胸腺癌など)、リンパ腫、奇形腫、神経原性腫瘍、縦隔内甲状腺腫、嚢胞性病変があります。手術適応は良性と考えられえる嚢胞性病変以外のすべてが対象となります。
手術は悪性の場合(胸腺腫、胸腺癌、リンパ腫など)でも血管や胸壁の周辺臓器の合併切除が必要ない場合は、胸腔鏡での手術が可能であることが多いです。5㎝を超える腫瘍や肺・大血管・心嚢に浸潤の可能性がある場合には胸骨正中切開や側方開胸が選択されます。胸腔鏡手術の場合、早ければ術後3-4日で退院可能です。開胸手術では、合併切除を要する大きな手術である場合がほとんどですが、術後5-10日程度で退院される方が多いです。
◇炎症性肺疾患について
通常は内科治療が対象となる疾患ですが、内科の治療が限界となり、手術により病状の改善が見込まれる場合に実施されます。手術対象となるものは肺非結核性抗酸菌症、肺真菌症(アスペルギルス症、クリプトコッカス症など)、膿胸(感染性の胸水貯留)などです。これらの疾患は高齢者、全身状態不良な方、免疫能が低下した方に多くみられるため、手術適応は本人や家族、担当の呼吸器内科医とも十分相談の上、実施されます。
肺抗酸菌症・真菌症に対しては胸腔鏡下に病巣を含めた肺切除を行いますが、胸の中の癒着がひどい場合は小開胸手術に移行することがあります。手術適応となる膿胸は胸腔ドレナージ(胸の中にチューブを入れて胸水を排液する方法)不成功例です。胸水が溜まったままであると、炎症が長引いて入院が長期化すること、肺が元通りに拡張しなくなるためです。手術は3㎝前後の傷が1-2か所で、胸腔鏡下に膿のかたまりと胸水を掻き出します。手術時間は胸の中の癒着の程度によりますが、おおむね1-2時間程度です。退院は術後の抗菌薬使用、全身状態などから決定されます。